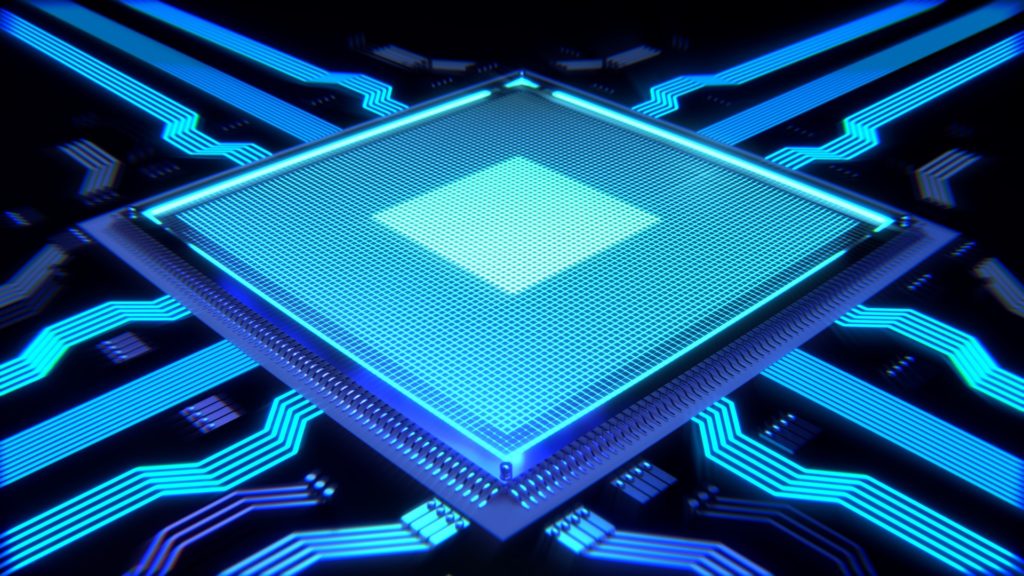
マイニングの演算アルゴリズムの処理に特化したASIC(エーシック)が登場すると、GPUでその通貨で収益を上げることが難しくなる。
ASIC(エーシック)とは?
通貨毎に、マイニングの演算アルゴリズムが決まっている。
ASICは、ある機能を処理することに専用化された集積回路のことである。
ある仮想通貨の演算アルゴリズムを処理することが可能なASICが登場すると、GPUでのマイニングでは太刀打ちすることが難しくなる。既にビットコインの演算アルゴリズム SH256A演算、そしてScryptという演算アルゴリズムを処理するためのASICは存在している。
特に問題なのは、仮想通貨の成り立ちが、中央集権的に通貨を発行管理するのではなく、ネットワーク上に分散化させて通貨の正当性を担保するという考えであったものが、ASICによって特定の個人や集団がマイニングの収益を独占しやすくなる = 中央集権化しやすい、という点だ。
仮想通貨の中には、ASICで処理することが難しい演算アルゴリズムを採用していることさえある。また、仮想通貨の正当性を担保する手法として演算能力だけではない別の指標が用いられるこも増えている(Pow→Pos)
一方で、仮想通貨の正当性を担保するためのマイニングによる膨大な電力消費を削減するために、より高性能なASICを開発して効率良く演算を処理すべきという考え方もある。
少し話が逸れるが、インターネットやSNSの普及によって、個人でも情報発信が可能になり、これにより社会の成り立ちが大きく変わりつつある。これまで中央集権的に情報が発信されていたものが、分散化されている個人からでも情報が発信され、拡散されることが大幅に増えた。
情報交換は人々を豊かにしてきたものだと思うし、このパラダイム・シフトは社会を良くするために大きな可能性を秘めていると思う(炎上が起きやすくなりこれまで以上に責められるようなことも増えているが)
仮想通貨、ブロックチェーン技術も、中央集権的だったお金の仕組み、またその他の中央集権的な社会の成り立ちを変えることが出来る可能性を秘めていると思う。
個人的には、GPUでマイニングを行っているので、マイニング用のASICが開発されることは好ましいことではないのだが、ASICの登場によって仮想通貨の正当性担保のための別の指標が登場してきたようにプラスな面もある。
今後もASICについての記事や、もう少し詳しい仮想通貨の正当性担保の指標について記事にしていこうと思う。

